今回は小学校に入学されたお子様を持たれる方向けに、本を読んで実践してみたことをまとめてみたいと思います。
子供が小学校に上がると勉強についていけるか等、心配事も多くなります。私もそうです。今回読んだ「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」では小学校1年から3年にかけてどのような時間にしたらよいかということが書かれていましたので紹介と実践したことを紹介したいと思います。
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」を読んだきっかけ
うちの子も小学生となり、子ども園の時とは生活のスタイルや学ぶ内容も変化してきました。テストや成績表なんかももらってきて、頑張れたこと、次に頑張りたいことなど話をしています。小学生1年から3年はとても伸びる時期で、学校の授業もそこまで忙しくないのでどのように取り組めばよいかと思い。こちらの本を手に取ってみました。
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」 要約
- 好きなことに熱中する時間を優先に
- ただひとつたっぷりさせたいことは読書
- 少なすぎるがちょうどよい毎日の学習。でも毎日確実に
- 遊びをとことん充実させる
- ウソをつかない。汚い言葉を使わせない。お手伝い。
| 書籍 | 小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」 |
|---|---|
| 著者 | 中根克明 |
| 出版社 | すばる舎 |
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」の著者 中根克明先生の紹介
著者の中根克明先生は、作文教室「言葉の森」の代表を務めていらっしゃいます。言葉の森は、作文の通信指導を行っており、毎週1回作文を書く、作文教育専門の教室です。幼稚園年長の子供から社会人まで1万2000人以上の生徒たちに作文を教えてこられました。
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」書籍構成と要約
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」は全部で5章の構成となっています。おわりにまでで223ページの書籍です。はじめにの部分では中根先生の言葉の森の話とどのような思いで、この本を書いたかが書かれています。1章では小学校1年から3年までの貴重な時間をどのように過ごしてほしいかその中で読書についておすすめしています。2章は読書にフォーカスしてどのような書籍がおすすめか、どのように読んでもらうのが良いかなど書かれています。3章は家庭での勉強方法についての方法。4章では遊び方について具体例も含めて書いてます。5章では、地力を持った子に育ってもらう為の親の注意点などが書かれていました。小学生低学年を持つ親にとってはとても役に立つ本だと思います。
はじめに:
1章:小1・小2・小3はとても貴重で大切な時期
2章:3年間の読書量で学力が決まる
3章:後伸びする低中学年の勉強法
4章:「遊び」をとことん充実させる
5章:本当に地力のある子に育てていく為に
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」書籍 要点
- 小学校1年から3年は格段に成長する。1年から3年の勉強はやればだれでもできる内容であり、まずは、家庭学習の習慣をつけることが大切。勉強をさっと終わらせてたっぷりと遊び、好きなことに熱中する時間をしっかりとってあげることが大切。
- 1年から3年でたっぷり読書を。読書こそ本当にしてもらいたい勉強。読むのに抵抗があるうちは、読み聞かせもとても有効。ここぞとばかり親子のコミュニケーションも大切にできる。1ページだけ読んでもらって残りは読み聞かせでも十分。おすすめの書籍は、易しくて面白い絵本、児童書がおすすめ。自然科学や伝記などの説明文にも触れておくと将来の読解力にも役に立つ。毎日10ページの読書を。付箋を貼ることでどこまで読んだか成果が分かるようにする。親も一緒に。読む力がつくから読むことが好きになる。小3までに本を読むことが面白いと思えるようになると最高
- 家庭学習は毎日1枚でも良い。やる習慣をつける。早く終わっても追加は厳禁。テストの点数はやれば上がるので、まずは勉強は明るく楽しく、親子で楽しむ時間を増やす。自分で準備して○つけまで自分でする仕組みづくりを。
- 特別なおもちゃがない方が夢中になれる!大量の紙、色鉛筆、粘土があれば楽しめる。自然の中での遊びや生き物を飼うことでもたくさん気づき学べる。実験的な遊びを取り入れることも良い。
- 一生の宝物となる経験を沢山してもらう。比較せず、本当に必要はしつけをする。ウソをつかせない、汚い言葉を使わせない、お手伝いをしてもらう。そうして地力のある子に育ってもらいたい。
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」を読んで実験してみたこと
今回こちらの本を読んで、読書、熱中、習慣、遊びといったキーワードが出てきました。うちの子に関していうと、テレビは好きですが、それよりも熱中することがあれば好きなテレビよりもそちらを選びます。空想遊びをしたければずっとそれをするし、今日も折り紙でパクパクカラスなるものを集中して作っていました。そんな中で、読書については、書かれていた内容の通り読むことの力が少ないためにどうも本を読むのは好きではないようです。
そのような理由から、読書と読み聞かせチャレンジを実施してみたいと思います。
少しのページでも読んでもらう。また、読みたくないというときは私と1ページづつ交互に読むなどして読み聞かせと読書をミックスしてみる。読む時間は夜だと私の帰りが遅い日もあるので、朝にやってみる。ここはやってみて修正はしてみたいと思います。
読んでみて変化や感想を本人に聞きながら検証してみたいと思います
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」読み聞かせの検証の結果
昔はよく寝る前に読み聞かせをしていたのですが、小学校入学後は私も仕事が忙しくなり、帰ったらもう寝ていたなどでなかなか読み聞かせができなかったです。
今回は、朝の時間を利用して5分でもいいので少しだけでも読んでもらう、一緒に読むをやってみました。
やはり本を読むのが好きではないらしく、スムーズに読書が習慣となることはなかったです・・・今も習慣化はできてないですのでここは根気よくです。
ただ、好きな本があるらしく、好きな本であればふとした瞬間に持ってきて自分で見てます(読んでいます)
よく読んでいたのは、「大ピンチずかん」「ハローキティのほうせきずかん」「おばけずかんシリーズ」なんかが好きみたいです。見てみると全部図鑑・・・
おばけずかんについては、ゲームブックもありそれが好きだと言っていました。
また、心理テストや占いの本なども好きならしく図書館や学校の図書室で借りて読んでいるようです。
毎日1ページづつ読めればいいかなと思い「国語好きな子に育つ楽しいお話し365」なんていうものも準備しました。小学校低学年にはちょっと難しいようで、こちらは読み聞かせがメインでした。
今日は○月○日の話にするわって感じで1ページ分読み聞かせをしていましたが、興味がある話とそうでない話の聞き方が全く異なることもよくわかりました。
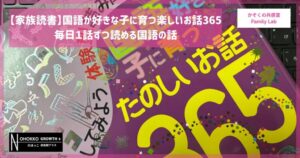
また、何か目的がしっかりあると読むようです。調べてみるとか、何か欲しいものがあって、毎日読書したらねというと本を持ってきて読んでいます。
本人的には、この本が面白いよとか言ってはくれているので、読む習慣までは言っていないけれどお気に入りの本などは作れていて自分で読もうかなと言う意思は少しは出てきた感じです。
「小学校最初の3年間で本当にさせたい「勉強」」をやってみた気づき・まとめ
習慣化するには、もう少し時間が必要そうですが、目的を決めることと、好きな本は読めるので、まあ興味がある本を何回でも良いので読んでもらうのが良いかなと思いました。
少しずつでも自分で積極的に読んでくれることは良いかなと思っています。私もそうですが、興味のあるものでないとなかなか本は読まないと思うので、色んな事に興味をもって調べる対象を増やしていけば、良いのかなとも思いました。
この間は宝石に興味があったので「ハローキティのほうせきずかん」をよく読んでいたし、今は心理テスト、占いに興味があるらしく「どろどろ~ん オバケーヌの心理テスト」を読みたいと言っていました。
興味のあることを聞いて、それに関連した本を読み聞かせや一緒に図書館で借りることで読書を促せるともいました。
この辺りはもう少し様子を見ながら読書や読み聞かせを続けていきたいと思います。
【次の本も子供の勉強に参考になりました】
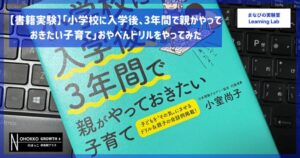
書籍実験の総まとめ記事はこちらにあります。書籍の要約ややってた変化などをまとめています。
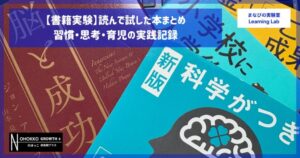
.png)
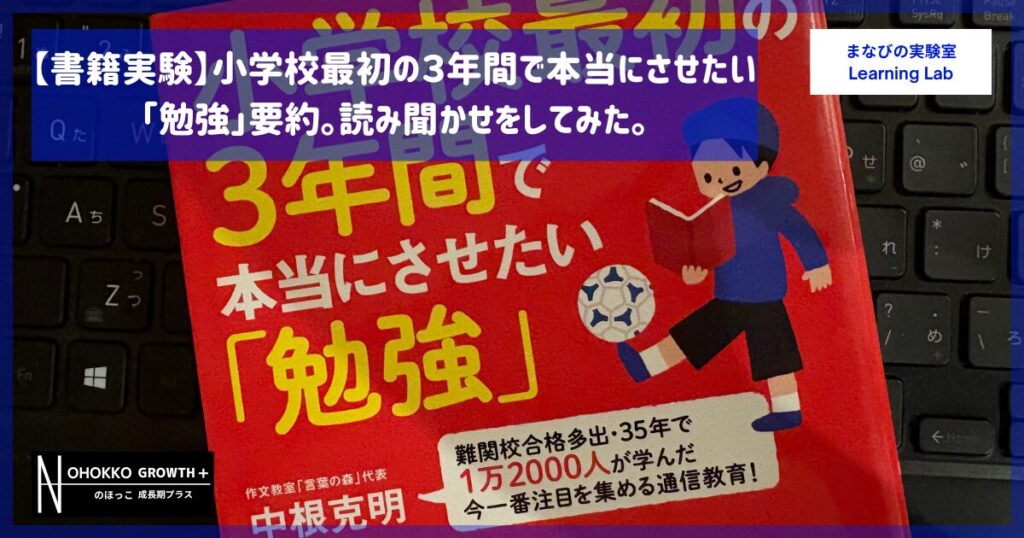

コメント