新学年にもすっかり慣れてきた夏前のこの時期。
小学校低学年の子どもたちは、学校や習い事でたくさんの刺激を受けながら、毎日を過ごしています。
そんな中で見落としがちなのが、「夜の過ごし方」や「睡眠時間」のこと。
まだまだ体も心も発達途中だからこそ、眠りのリズムを整えてあげることが、子どもの元気と笑顔につながります。
この記事では、小学校低学年の睡眠時間の目安や、夜の“おうちリズム”をどう整えていくかをテーマに、
実際の暮らしの中で取り入れやすいヒントや工夫を、やさしくお届けします。
明日の朝、「おはよう」がちょっと心地よくなるような、そんな眠るまでの流れを、一緒に考えてみませんか?
小学校低学年の睡眠時間、どれくらいがちょうどいい?
必要な睡眠時間は何時間?文科省や小児科の目安
文部科学省や日本小児科学会が発表しているガイドラインによると、小学校低学年(6〜8歳)の子どもには、1日9〜11時間の睡眠が推奨されています。
たとえば夜9時に寝て朝6時に起きる、そんなリズムが理想的。ただし、家庭ごとに生活スタイルは異なります。共働きや習い事、兄弟姉妹のスケジュールに左右され、現実には理想通りにいかないことも多いもの。
とはいえ、「寝る時間を確保する」ことだけでなく、安心して深く眠れる環境づくりも大切です。睡眠の“質”にも注目していきましょう。
睡眠不足が子どもに与える影響とは?
子どもの睡眠不足は、単なる“眠そう”だけでは済まない影響を与えることも。
- 朝起きるのがつらい
- 集中力が低下する
- イライラしやすくなる
- 食欲が落ちる
また、睡眠中には「成長ホルモン」の分泌が活発になります。十分な睡眠をとっている子どもは、体の成長や免疫力、記憶の定着などにも良い影響があるといわれています。
だからこそ、小さなうちから「よく眠る」習慣を整えてあげることが、子どもの未来への投資につながります。
「早寝早起き」はどうして難しい?おうちのリズムを見直すヒント
「早く寝かせたいけれど、気づいたら21時半を過ぎてしまう」──よくある悩みです。
まずは、夜の過ごし方をちょっとだけ見直してみませんか?
- 帰宅〜就寝までの時間の流れをざっくり決める
- スマホやテレビをつけっぱなしにしない
- 親も一緒に眠るモードへ切り替える
たとえば、「お風呂のあとは部屋の照明を落とす」「一緒に布団に入って本を読む」など、夜時間に“合図”をつけると、自然と体も心も眠る準備が整いやすくなります。
わが家の“夜時間”ルーティン
お風呂・ごはん・ゆっくりタイムの流れ
夕方からの流れは、ざっくりこのような感じです:
- 18:00 夕ごはん:家族そろって食卓を囲む
- 18:45 お風呂:湯船にゆっくり浸かってリラックス
- 19:30〜 静かな遊び:テレビを消し、読書やぬりえ、折り紙など
「◯時に寝かせなきゃ」よりも、「◯時から夜の準備を始めよう」という感覚に変えると、子どもも大人も気持ちが楽になります。
大体、8時くらいを目安に寝ていますが、早い時は7時台に寝ている時も・・・朝は5時台に起きているので、9~10時間の睡眠をとっている感じです。とてつもなくぐっすり寝ていますね。
夜の親子対話で、心も落ち着く時間に
寝る前に5〜10分、子どもの今日のことを“ただ聞く”時間をとるようにしています。
「今日どんなことがあった?」「どんな気分だった?」とゆっくり問いかけると、思いのほかたくさんのことを話してくれるものです。
忙しいとついスキップしてしまいがちですが、心が整う時間=眠りの質が上がる時間でもあるのだと実感しています。
眠る前5分の「今日のうれしいこと」と小さなおまじない
布団に入って電気を消したあと、こんな問いかけをしてみます。
「今日、うれしいことあった?ありがとうって思ったことある?」
うーん。
- 「友だちが折り紙くれた」
- 「給食が美味しかった」
など、だんだんと言葉が出てくるように。
ポジティブな気持ちを持って眠ることは、次の日の元気にもつながります。
子どもが“ぐっすり眠る”ためにできること
寝る前の光・音・言葉を整える
眠る30分前から照明を落とし、音を静かに。
「早く寝なさい!」という強い言葉より、「そろそろおふとんに行こうか」と穏やかに声をかけることで、子どもの心にも安心感が生まれます。
親のイライラは、子どもにダイレクトに伝わるもの。まずは親が“眠るモード”になることから始めてみましょう。
うちはわりと「寝るよー」と言えば、えーと言いながらも、「グッナイ!」といって布団に入ってってます。
【枕元におすすめの可愛い猫ライト】
朝が気持ちよく始まる「眠りの仕込み」
- 寝る前に一口の水をとる
- カーテンを少し開けておく
- 朝起きたら聞く音楽を決めておく
など、“朝のための準備”を夜にしておくと、翌朝のスタートがスムーズに。
「怒る朝」より、「穏やかな夜」の積み重ねが、毎朝気持ちの良い家庭のリズムを整える鍵になると感じます。
「寝かせなきゃ」から「眠れる準備をする」へ
「早く寝て!」の焦りは、子どもに伝わりやすいもの。
「眠れるように環境を整えてあげよう」というスタンスに切り替えるだけで、子どももスッと布団に入るようになります。
- 好きな絵本を1冊読む
- 柔らかい声で話しかける
- 寝室に香りや音楽を取り入れる
“眠りの支度”は、子どもとの関係性も整えてくれる時間になるはずです。
おわりに|よく眠った朝は、ちょっとやさしい
小学校低学年の子どもにとって、睡眠は「こころ」「からだ」「学び」の土台。
大人の関わり方ひとつで、その質も変わっていきます。
忙しい日々の中でも、「今日は眠りの準備、ちょっと丁寧にしてみようかな」と思えたら、それがきっと親子の暮らしをやさしく整える第一歩になるはず。
「今日もよく眠れたね」
そんな朝が、少しずつ増えていきますように。皆さんも子どもの成長の為に、気持ちの良い朝を迎えるために。
色々と整えてみてはいかがでしょう

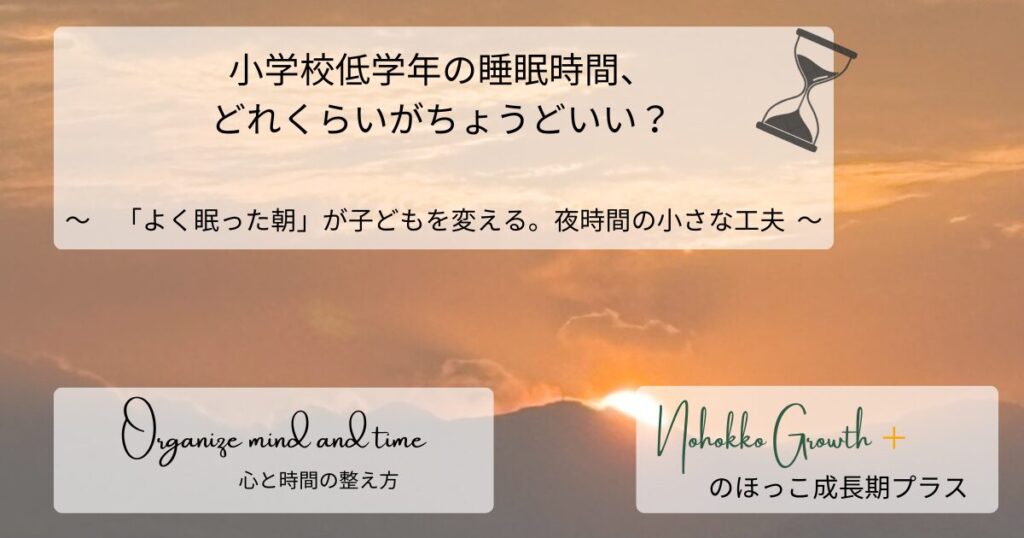
コメント