夏の陽ざしが日に日に強くなる季節。子どもたちが外で過ごす時間が増える今、「日傘って必要?」と気になっている方も多いかもしれません。熱中症や紫外線の影響を考えると、帽子だけでは守りきれない部分もあります。
実は、子どもが使う日傘の“涼しい効果”は想像以上。体感温度を下げてくれるだけでなく、小さめサイズで軽く、安全に使える工夫がされた製品も登場しています。
一方で、「禁止されている学校もある」という現実や、「そもそも子どもに日傘ってどうなの?」という声も。
この記事では、子ども用日傘の効果やメリット・デメリット、安全性や選び方、そして親子でどう向き合うかを、やさしく解きほぐしていきます。
これからの夏を、子どもと一緒に“涼しく、心地よく”過ごすためのヒントになればうれしいです。
そもそも、子どもに日傘って必要なの?
熱中症対策や紫外線の影響、日傘の“涼しい効果”
真夏の太陽の下、ぐんぐんと気温が上がる中で過ごす子どもたち。実は私たち大人以上に、子どもは気温の変化や紫外線の影響を強く受けやすい存在です。特に小学生低学年くらいの年齢では、体温調節機能がまだ発達途中のため、暑さへの対応力が十分とは言えません。
そこで注目されているのが「日傘」です。帽子では守りきれない肩や背中、腕などを広範囲で日陰にしてくれる日傘は、体感温度が3〜7℃も下がるともいわれています。最大で7~10℃といった情報も!「なんだか涼しいね」と、子ども自身が実感できる小さな快適さは、夏を過ごす大きな支えになります。
また、強い日差しによる肌トラブルや日焼けからも優しく守ってくれる日傘は、健康面でも頼れるアイテム。毎年暑さが厳しくなる中、親子で見直したい夏の過ごし方のひとつです。
「帽子とどう違うの?」日傘を使うメリット・デメリット
帽子と日傘、どちらも暑さ対策に有効ですが、それぞれに異なる良さと特性があります。
【帽子のメリット】
- 両手が自由に使えるため活動的
- 通園や通学での利用が日常的で慣れている
- 強風の中でも使いやすい
【日傘のメリット】
- 頭だけでなく体全体を日陰にできる
- 暑さと日差しの両方を効果的にカット
- UVカット率の高い素材で肌をしっかり保護
一方で、日傘は片手がふさがってしまうことがあるため、使う場面や環境に応じた工夫も大切。状況に応じて使い分けたり、日傘を使う日の行動をあらかじめ計画したりと、親子で相談しながら上手に取り入れていくのがよさそうです。
子ども用の日傘、どう選べばいい?
「軽くて小さめ」の日傘がおすすめ|子どもに合うサイズ感とは
日傘をはじめて使う子どもにとって、軽くて扱いやすいことはとても大切。大人が何気なく使っているサイズでは大きすぎて扱いにくく、逆に危険な場合もあります。
【選び方のポイント】
- 全長50〜60cm程度のミニサイズがベスト
- 重量200g以内で軽量タイプ
- 小さな手でも握りやすいグリップ付き
- 折りたたみ式でランドセルにも収納可
お気に入りのカラーやキャラクター柄を選ぶのも楽しく使えるポイント。自分のものとしての愛着がわくことで、自然と持ち歩く習慣もつきやすくなります。
軽くて折り畳み式で可愛いがらも。お祝い用にも
安全性もチェック|日傘の開閉や骨のつくりにも注目
日傘は安全性にも配慮して選びたいもの。子どもが自分で開閉する場面を想定し、操作しやすく、怪我をしにくい作りのものを選びましょう。
【安全面のチェックポイント】
- 指を挟みにくい「安全ストッパー」付き
- 柔軟性があり折れにくい骨組み(グラスファイバー製など)
- UVカット率90%以上の遮熱・遮光素材
- 傘の先端が丸く、安全カバーがあるか
これらのポイントを抑えることで、子ども自身が安心して使える日傘に出会うことができます。
親子でシェアできる?年齢別おすすめタイプ
低学年まではコンパクトで軽いものが扱いやすくおすすめ。中学年〜高学年になれば、シンプルで大人と共用できるデザインも検討できます。
兄弟姉妹で使いまわせるよう、ユニセックスな色合いを選んだり、複数使いができる工夫も嬉しいですね。親子で日傘を使う楽しさを共有することで、使うことへの抵抗感も薄れていくかもしれません。
大人も子供も女性も男性もみんな使える仕様
学校や園での「日傘禁止」問題と向き合うには
なぜ禁止される?学校側のルールや理由
「せっかく買ったのに、学校では使えない…」という声を耳にすることも。現在も、保育園や小学校で日傘が禁止されているといった声が聴こえてきます。
その背景には、
- 片手がふさがって通学が危ない
- 保管場所がなく扱いが難しい
- 家庭によって用意できる・できない差が出る といった、安全性や公平性を重視する視点があります。
先生や地域社会が子どもたちの安全を守ろうとする姿勢のひとつとして理解することも大切です。
禁止でもできる“涼しく過ごす工夫”
たとえ日傘が使えなくても、暑さから子どもを守る方法は他にもたくさんあります。
- 通気性がよく、つばの広い帽子を選ぶ
- 首元を冷やす冷感タオルの使用
- 通学路で日陰を探して歩く工夫
- 水筒の中身を凍らせて持たせる
- 暑さ指数(WBGT)をチェックして外出判断
“できること”をひとつでも増やす視点で、無理なく取り組める工夫を親子で探していきましょう。
「話し合ってみる」も選択肢に。地域や学校で違う実情
全国の中には、熱中症リスクが高まる現代の気候を受け、子どもの日傘を認める動きが広がってきている地域もあります。
「うちの子の通学路は日陰がないから…」「実は日傘の方が安全かも」そんな声をきっかけに、学校と保護者が話し合い、柔軟な対応を実現するケースも増えています。
大切なのは「一緒に子どもを守る方法を考える」こと。保護者同士での情報共有も、変化の第一歩になるかもしれません。
のほっこ流|子どもと一緒に考える「夏の過ごし方」
「日傘は大人だけのもの?」を問いなおす
昔ながらのイメージとして、日傘は「女性のもの」「大人の持ち物」といった印象が根強くあります。でも今は、性別や年齢を問わず“涼しさを守るツール”として見直されている時代。
「女の子じゃないと変かな?」「ぼくも持ってみたい」――そんな子どもの気持ちに寄り添うことで、日傘の新しい役割を広げていけたら素敵ですね。
晴雨兼用の可愛い折り畳み
暑さを“感じて・考える”ことも立派な学び
「どうしたら少しでも涼しくなるかな?」と考えることは、子ども自身が自分の体を大切にしようとする“暮らしの感性”を育てることにもつながります。
暑さ対策という視点だけでなく、「環境に合わせて自分で工夫する」ことを学ぶチャンスとして、夏の生活を見つめ直してみるのもおすすめです。
「どうしたら快適かな?」と親子で考える時間を大切に
答えはひとつではなくていい。暑さの乗り越え方も、家庭ごとのスタイルでいい。
「今日は日傘にする?」「お昼からは日陰の道を選ぼうか」など、小さな問いかけや会話が、子どもの“感じる力”と“考える力”を育てていきます。
夏の毎日を、少しでも心地よく過ごせるように。のほっこの世界では、そんなやさしい選択を大切にしています。
暑さと仲良く付き合いながら、子どもたちと一緒に“涼しい工夫”を楽しむ夏にしていきましょう。
可愛い人気キャラクターの日傘も

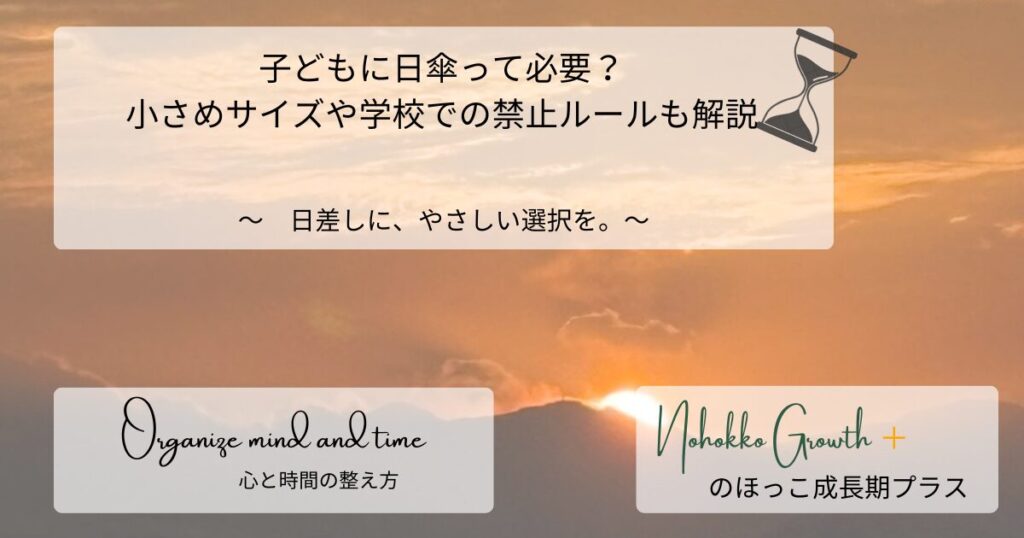
コメント