夏休みといえば、自由研究や絵日記など、たくさんの小学生の宿題が待っています。その中でも「作文」は、毎年親子で悩む課題のひとつ。とくに書き方やテーマの選び方に迷うことも多く、「どうやって始めればいいの?」と戸惑う声もよく聞きます。
また、学校の宿題だけでなく、地域や新聞社などのコンクールへの応募を考えている家庭にとっては、作文の内容や構成にもっと工夫が必要になることも。
このページでは、夏休みの作文をスムーズに書き始めるためのヒントや、小学校低学年でも取り組みやすいテーマ、親子でできるサポートのコツまでをご紹介。
「うちの子にも書けそう!」と感じられるような、やさしいガイドを目指しています。
夏休みの作文、どこから手をつけたらいい?
宿題?コンクール?まずは目的をチェック
夏休みに入ると、子どもたちの宿題リストの中に必ずある「作文」。けれど、いざ書こうとすると、鉛筆が止まったまま……という声も少なくありません。
まずは、作文の”目的”を確認することが大切です。
- 学校の宿題として出されたものなのか
- 地域や新聞社などのコンクール応募を前提としたものなのか
目的によって、求められる内容や長さ、提出形式が変わってきます。コンクール用であれば、少し時間をかけてテーマ選びから丁寧に。宿題ならば、日常の中での発見や経験を中心に選ぶとスムーズです。
親が最初にできるサポートは、「どんな作文が必要なのか」を子どもと一緒に確認すること。そこから自然と、次にやるべきことが見えてきます。書き始めのハードルがぐっと下がるでしょう。
「何を書けばいいの?」がわかる、テーマの選び方
テーマに悩むときは、まずは子ども自身が「心が動いた瞬間」に注目してみましょう。
- どきどきした
- びっくりした
- うれしかった
- ちょっと悲しかった
そんな気持ちが動いた瞬間を思い出すことで、作文の糸口が見えてきます。
また、「○○へ行った」「○○をした」という行動の裏にある気持ちを引き出す問いかけも効果的です。
「それって、どうだった?」「どんな気持ちになった?」
こういった声かけにより、出来事が“自分のことば”で語れるようになります。作文がグッと身近に感じられるはずです。
子どもが書きやすいのは“できごと×気持ち”の作文
難しい言い回しや立派な文章よりも、子ども自身が体験したことと、そこに重なる感情を結びつけた作文が、一番伝わりやすく、書きやすいのです。
「水族館でイルカのショーを見た。水しぶきがかかって冷たくて、でもすごく楽しかった」
このように、できごとの描写に自分の感情がのっていると、それだけで“伝わる作文”になります。親は無理に直さず、言葉選びの自由さを大切に見守りましょう。
小学生でも書きやすい!夏の作文テーマ例
1・2年生向け|「はじめて」「びっくりした」体験を書く
低学年の子には、身近でわくわくした出来事をテーマにするのがおすすめです。
- はじめて金魚すくいをした
- びっくりするくらい大きなスイカを見た
- 初めて育てたピーマンを収穫した
「いつ・どこで・なにをして・どう思ったか」を中心に構成すると、無理なく作文にまとめることができます。五感を活かすと、文章がよりいきいきします。
3・4年生向け|自分の考えを入れた「気づき作文」
中学年前後の子どもたちは、経験を通じて「気づき」や「学び」を感じる力がぐんと伸びます。
- 図書館で見つけた本を読んで考えたこと
- おじいちゃんと釣りに行って感じたこと
- 毎日水やりして咲いた朝顔から学んだこと
こうした“気づき”を入れた作文は、心の成長も感じられて読み手にも響きます。観察力や表現力を自然と育てるテーマとしてもぴったりです。
夏らしさを取り入れる|季節のにおいや音をことばに
せっかくの夏休み、季節感を活かした作文もおすすめです。
- セミの声がやまびこのように響いていた
- 夕立のあと、道路から立ちのぼる蒸気のにおい
- 夕方の風がちょっとだけ秋の気配を運んできた
五感を使ったことばは、作文をぐっと豊かにしてくれます。におい、音、色、感触を思い出すと、自然と表現の幅が広がります。ちょっとした、ことば選びなども楽しいと思います。
作文は、出来事そのものよりも、そのときの「気持ち」をどうことばにするかが大切です。子どもが自由に自分のことばを使って表現できるよう、見守る大人は「こう書いたほうがいい」という指導よりも、「こんなふうに思ったんだね」と、心に寄り添う姿勢で関わってあげたいですね。
作文がぐんと書きやすくなる“3つのコツ”
①「いつ・どこで・だれが・なにを」で書き出す
作文の出だしに迷ったときは、この4つを意識してみましょう。
「8月のある日、わたしは家族と川へ行きました」
これだけで、読み手に場面が伝わります。そのあとの展開が広げやすくなるのもポイントです。特に、状況が明確な導入は、読者の想像力を助けます。
②「気持ちが動いた瞬間」をことばにする
ただの事実だけを並べるのではなく、自分の感情をことばにしてあげると、作文は一気に“自分のもの”になります。
「魚が釣れたとき、うれしさで心がドキドキした」 「転んでしまったけど、立ち上がって歩けたとき、少し自信がついた」
感情を入れることで、読んだ人の心にも届く作文になります。自分だけの経験として、言葉が輝きます。
③最後に「思ったこと・これからどうしたい」を入れる
締めくくりには、その体験を通して何を感じたのか、これからどうしていきたいのかを書くとまとまりがよくなります。
「また来年もおじいちゃんと釣りに行きたい」 「もっと字をきれいに書けるように練習したい」
未来へのつながりが見えると、作文に余韻が残ります。読んだ人に想いが届く構成になります。
おうちでできる、作文サポートのヒント
「なんでそう思ったの?」を聞いてあげるだけでOK
作文を書かせようとする前に、子どもとおしゃべりしてみましょう。
「そのとき、どう思った?」「なんでうれしかったの?」
こうした問いかけが、作文の“たね”になります。親の問いかけは、子どもが自分の内面に気づくきっかけになります。
話す→書く で、ことばを整理するお手伝いを
いきなり紙に書こうとすると、ハードルが高く感じてしまいます。
まずは話すことから。
「じゃあ、それを書いてみようか」と自然な流れで書く作業に入れると、子どもも安心して取り組めます。話すことで頭の中が整理され、書き出しやすくなるのです。
書いたあとは“がんばったね”の承認を忘れずに
書き終えたあとのひと言が、子どもの自信につながります。
「よくがんばったね」「気持ちがよく伝わってきたよ」
結果ではなく“書いたこと”そのものを認めてあげることで、書くことが好きになっていくはずです。親の承認は、次のやる気を生みます。
おわりに|作文は“ことばの宝もの”
うまく書けなくても、それが“いまの気持ち”
大人のように整った文章じゃなくていい。 子どもが「こう思った」「こんなことがあった」を自分のことばで綴る、それだけで立派な作文です。
書くという行為は、いまの自分を見つめる時間でもあります。子どもの心の記録としても大切にしてあげたいですね。
親子で作文を“楽しむ”夏にしよう
夏休みの作文は、親子の時間を豊かにしてくれるチャンスでもあります。
「一緒にテーマを考える」「ちょっとした会話から作文にしてみる」
そんなやりとりが、“書くっておもしろい”という気持ちを育ててくれるはず。
ことばの宝ものを、親子で大切に育てる夏になりますように。小さな文章が、大きな思い出になりますように。
そんなことを感じながら、作文を書くための助けとなればよいかと思います。
あると便利な道具たち。
手元を明るくして目が疲れないように【スタンドライト】
鉛筆の持ち方や疲れ軽減に【鉛筆グリップ】
.png)
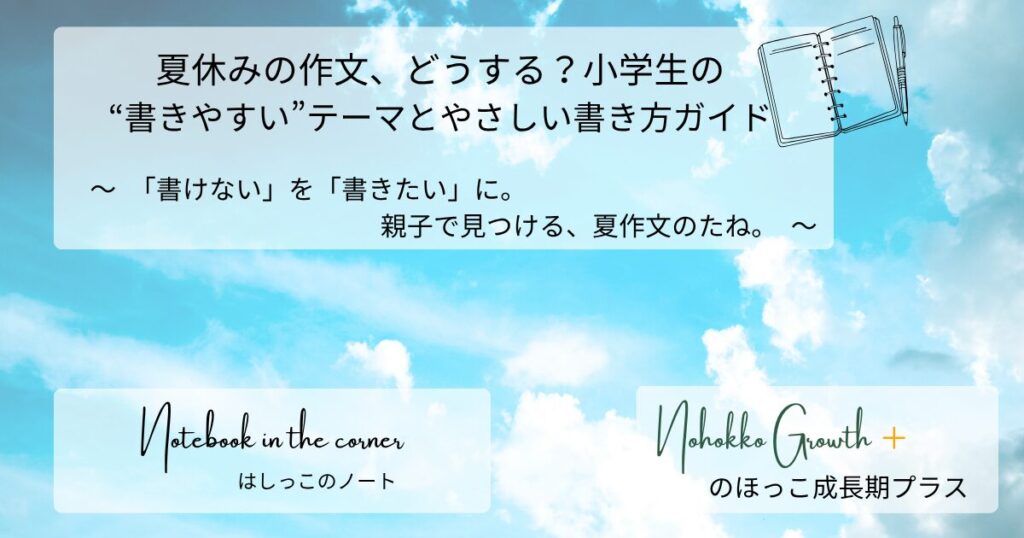
コメント